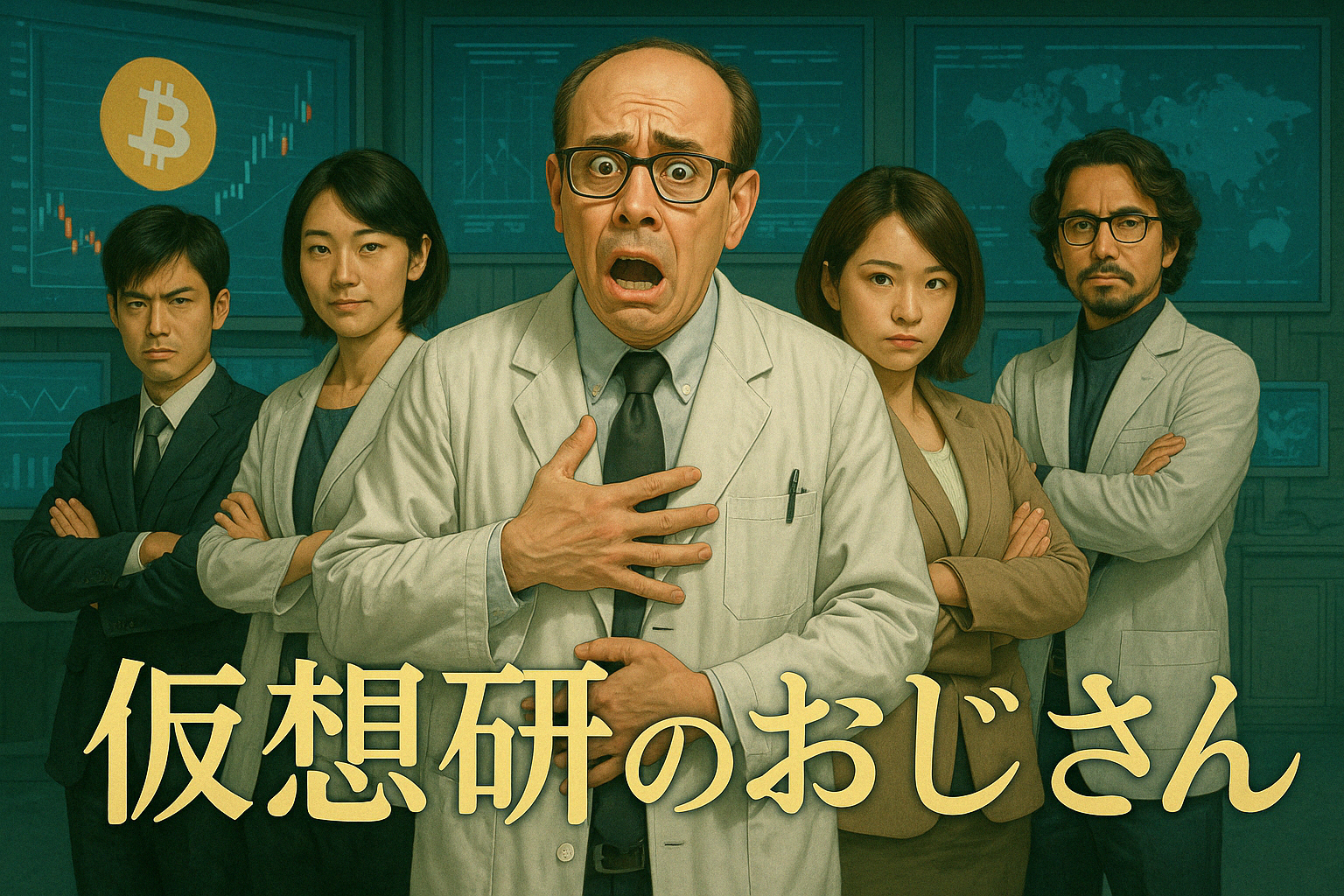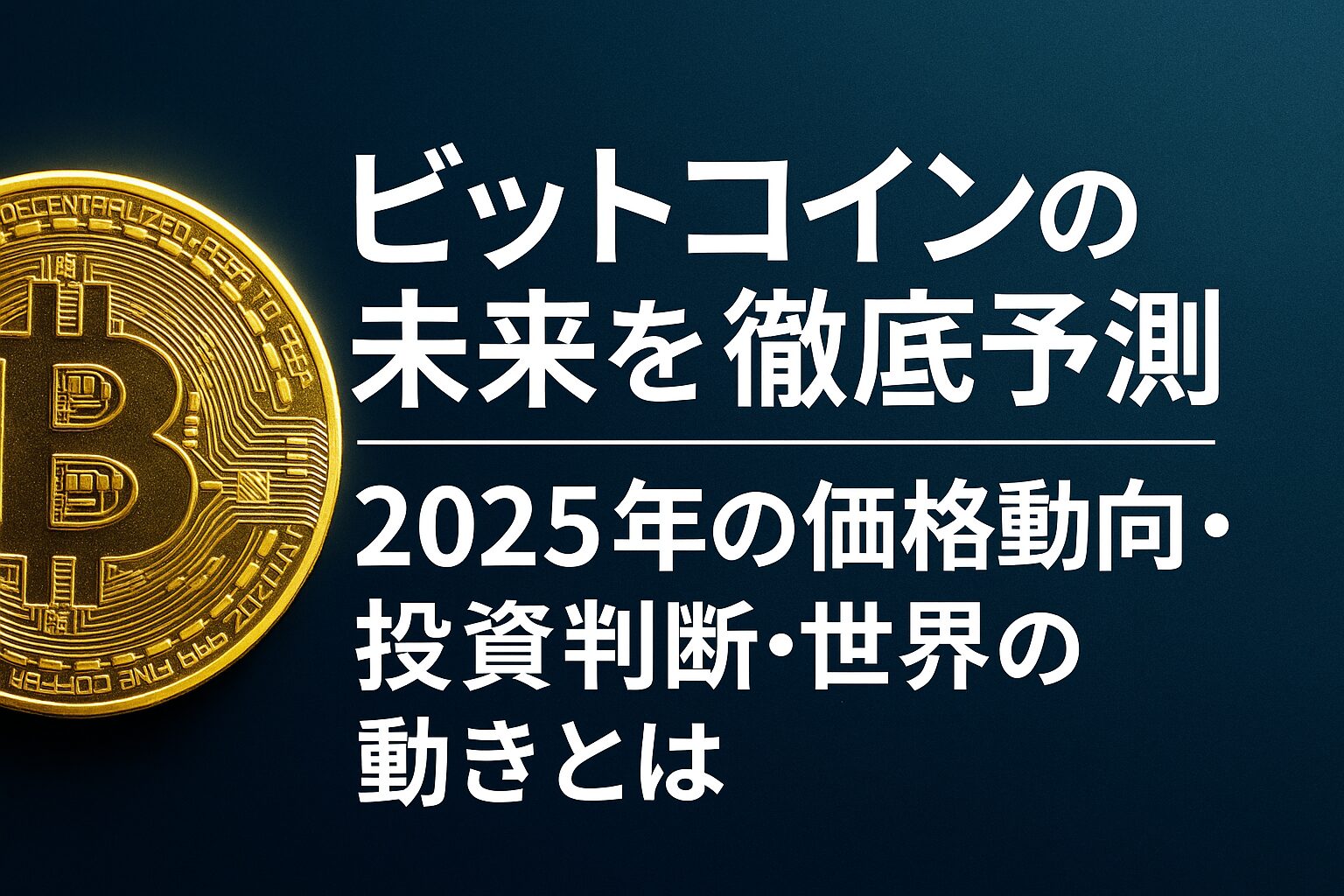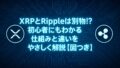こんにちは、仮想研のおじさんです。
2025年に入り、ビットコインは今まで以上に注目を浴びています。
価格は9万ドルを超え、国家や機関投資家も積極的に関与し始めていますが、その一方で欧州などでは慎重な姿勢も見られ、世界は二極化しているのが現状。
この記事では、ビットコインに対する世界の賛否両論を2025年の最新情報に基づいて整理し、おじさん目線でどう向き合うべきかを、おじさんが、やさーしく、解説していきますよ。
ビットコインに「賛成」する国・企業・金融機関の動き
🌍 国家レベルの動向
- アメリカ:2024年末から2025年にかけて、複数の現物型ビットコインETF(BlackRock, Fidelity, Franklin Templetonなど)がSECに承認され、機関投資家の資金流入が拡大。
- エルサルバドル:2021年にビットコインを法定通貨化。2024年には準備金としての運用に注力。ただし、国内経済との摩擦から一部政策見直しの動きも。
- スイス・シンガポール・UAE:暗号資産を戦略資産と認識し、中央銀行が規制と共存の道を模索。
🏦 金融機関の動き
- BlackRock(ブラックロック):世界最大の資産運用会社が「iShares Bitcoin Trust」を開始し、10億ドル規模の資金を集めた。
- Franklin Templeton、Fidelity:自社のETFも承認され、401(k)(米国の年金制度)での組み入れを進行中。
- Morgan Stanley、Goldman Sachs:顧客向けに暗号資産商品の提供を再開。資産管理部門でビットコインへの配分を許可。
🏢 大企業・年金基金の参入
- MicroStrategy:2025年3月までに合計21万BTC以上を保有し、企業として最大のビットコイン長期保有者。
- Tesla:2024年末の四半期決算で再びBTC保有を報告。
- カナダ年金投資委員会(CPP)やノルウェー政府年金基金も、ETF経由でビットコインへの間接投資を開始。
🇯🇵 ソフトバンクの動き
- 2025年初頭、ソフトバンクが米国市場でビットコインETFを通じた投資を一部開始との報道あり。公式には否定していないが、技術系スタートアップの暗号資産導入に支援を行っている。
これらの動きは、ビットコインを「投機対象」ではなく「資産クラス」として位置づける機運の高まりを示しています。
ビットコインに否定・慎重な国の姿勢
🇪🇺 EU(欧州連合)
- 2024年後半、欧州中央銀行(ECB)が「ビットコインを法定準備資産として認める予定はない」と明言。
- デジタルユーロの導入準備が進む中で、ビットコインを通貨として認めることは「政策的に矛盾」との見解。
🇨🇳 中国
- マイニング全面禁止に加え、個人のビットコイン保有は容認されつつも、取引所・決済での利用は依然として厳しく制限。
- デジタル人民元(e-CNY)を国家戦略として推進し、ビットコインは「国家主権に対する脅威」と位置付け。
🇮🇳 インド
- 2025年時点で依然として不透明な法規制が続く。大手取引所への課税強化やKYC強化により、個人投資家の取引量が減少。
- RBI(インド準備銀行)は「価値保存手段としての信頼性が欠如」と公式声明を出す。
その他の懐疑的な動き
- **国際決済銀行(BIS)**やIMFも、ビットコインを「通貨としては不適切」「投機的資産」として位置付け。
- 日本の財務省・金融庁も2025年初に「公的準備資産としての導入予定はない」と明言。
- 気候変動対策に積極的な国々(オランダ、デンマークなど)はマイニング規制の議論を進めており、「環境負荷の高い資産」として警戒感を強めている。
このように、ビットコインを積極的に受け入れる国や機関がある一方で、通貨主権、金融安定、環境といった観点から否定・懸念の声も根強く残っています。
技術と環境から見たビットコインの懸念点
🔌 電力と環境問題
ビットコインのマイニング(採掘)は、ブロックチェーンの安全性を保つために大量の電力を必要とします。
これは環境負荷を生み出し、特に火力発電に依存する地域ではCO2排出の問題が深刻です。
また、生成AIなども急速に電力を消費するため、今後は電力リソースの取り合いになる可能性も指摘されています。
📉 スケーラビリティと手数料
ビットコインは、1秒間に処理できる取引件数が非常に少ない(約7件/秒)ため、大量取引に不向きです。
その結果、送金詰まりが発生しやすく、手数料も上がりやすいという課題があります。
🧾 補足:レイヤー2やライトニングネットワークとは?
こうした問題を解決するために開発されたのが「レイヤー2ソリューション」です。これは本体のビットコインブロックチェーンとは別の“高速道路”のような技術で、ライトニングネットワークはその代表例です。
簡単に言うと、「まとめて処理して、後で清算する」ことで、スピードと手数料を抑えています。
⚠️ ブロックチェーンの根本思想と矛盾する可能性
ただし、このライトニングネットワークの仕組みには矛盾もあります。
- 通常のビットコインは「すべての取引履歴がブロックチェーンに記録されること」で透明性と検証性を保っています。
- しかし、ライトニングでは「オフチェーン」でのやり取りが基本で、実際の取引内容はブロックチェーンに記録されないのです。
- つまり、「いつ誰が誰に送ったか」といった情報は確認できず、ブロックチェーンの意味が一部失われるという指摘もあります。
ライトニングネットワークは、スピードやコストの面では優れていますが、透明性や改ざん耐性といったブロックチェーン本来の価値とトレードオフになっているという点は押さえておきましょう。
🧠 量子コンピュータの脅威
量子コンピュータの発展により、現在の暗号技術が将来破られる可能性があると警告されています。
ビットコインのような公開鍵暗号方式は、特定のアルゴリズムによって成り立っているため、それが破られるとセキュリティの根幹が揺らぐことになります。
このリスクに備え、量子耐性を持つ暗号技術の研究も進んでいますが、実用化には時間がかかるとされています。
🔄 他通貨との競争と「発行上限」の再考
ビットコインは「発行上限がある」=「インフレしにくい」ため、価値の保存手段として支持されてきました。
しかし、実は発行上限が設定されている仮想通貨は他にも多数存在します。
- Litecoin(LTC):最大8400万枚
- Stellar(XLM):最大500億枚(供給上限に達し、今後の増刷はない)
- Cardano(ADA):最大450億枚
- Polkadot(DOT)、**Avalanche(AVAX)**なども供給設計が工夫されています
また、以下のような仮想通貨は、ビットコインの欠点(スケーラビリティ・手数料・電力問題・量子脅威など)を克服する設計となっています。
- Stellar(XLM):処理速度が速く、手数料も極めて低い。国際送金にも利用可能。
- Algorand(ALGO):省電力かつ高速決済が可能。量子耐性アルゴリズムにも対応予定。
- Cardano(ADA):PoS(プルーフ・オブ・ステーク)による低エネルギーなブロックチェーン。
- IOTA(MIOTA):ブロックチェーンを使わず、IoT向けに最適化された軽量システム。
つまり、ビットコインの技術的特徴が唯一無二ではなくなってきているのです。
「発行上限=価値保存手段」という見方は重要ですが、それが“ビットコインでなければならない理由”になるかどうかは、今後の市場の成熟度や利便性によって左右されていくでしょう。
まとめ:ビットコインは「幻想」か、それとも「現実」か?
2025年、ビットコインは国家・企業・機関投資家が真剣に向き合う存在になりました。
しかし、その一方で否定的な見解や技術的な課題も健在。
世界が割れている今こそ、「情報をもとに、自分で考え、判断する」力が試される時代です。
仮想研のおじさんのひとこと:

「みんなが買ってるから安心」
って、それが一番危ない。
ビットコインも完全な安全資産ではないのです。
投資の世界は、
「まさか!!」
ということも度々あることを知っておきましょう。
しかしながら、仮想通貨、ブロックチェーンの未来は明るいことは確か。
仮想通貨もビットコインだけに集中投資するのではなく、他の仮想通貨に分散投資するのも、リスク回避手段の一つです。